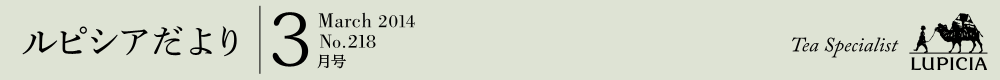中国神話時代の医薬と農業の開祖、神農によって発見されたというお茶。はじめは薬草と考えられていましたが、紀元前世紀の前漢時代にはすでに喫茶の記録があり、早くも7世紀の唐代には、陸羽が『茶経』を著して喫茶を楽しむ文化を確立しています。
日本では平安時代に空海や最澄などの留学僧が唐から持ち帰った記録があります。鎌倉時代には栄西が、宋で会得した抹茶の飲み方を伝え、それが茶の湯文化の原点になりました。
ビタミンやミネラルが豊富で香り高く、カフェインのおかげで気分もすっきりするお茶は、お酒と違って酔うこともなく、会話やコミュニケーションを活性化させるのにうってつけの飲み物として扱われてきました。
お茶はヨーロッパに伝わっても、コミュニケーションの飲み物として受け入れられます。17世紀のオランダでは、貴婦人たちの間で日本の茶の湯をまねたお茶の飲み方が大流行しました。英国流のティーパーティーも、実はそこから発展していったというわけです。
つまりは現代の「ねえ、お茶しない?」というナンパの言葉にだって、千年以上の歴史があるということ。そんなお茶のコミュニケーションに役立つ、とっておきの7つの知恵をご紹介。この春あなたも試してみませんか?


英国式紅茶術=ゴールデンルールというと、ちょっと難しそうなイメージがあります。でも実際には、英国流の合理主義が育んだ、とてもシンプルな紅茶のいれ方。烏龍茶にもそのまま応用できます。
それでは、その5つのポイントを取りあげてみましょう。
① 茶葉はいいものを選ぶ、②あらかじめポットは温めておく、③茶葉は1人につきティースプーン1杯+ポットのためにもう1杯、④沸かしたてのお湯を使い、⑤浸出時間を待つ。以上です。これっていつもやっていることだと思いませんか?
ちなみに③の「ポットのためにもう1杯」は、お茶の風味が出にくい硬水が多い英国ならではのルール。また、ゴールデンドロップという最後の1滴までお茶を完全に注ぎ切ることを強調した表現も、2煎めをよりおいしくいれるための約束事なのです。だから「これがゴールデンルールよ!」と胸を張って、いつものとおりお茶をいれれば、それでもう、あなたはティーマスターです。


ホームパーティーなどで、大人数にお茶を注ぎ分けるのは難しい、と思っていませんか? さっと手際よく、みんなにおいしいお茶がいれられたら、それだけでポイント急上昇のはずなのに……。
実はこれ、とても簡単なことなんです。日本茶でも紅茶でも、ポットや急須を2本用意するだけ。片方でお茶を浸出させたら、もう一方の空のポットに注ぎ切ります。人数が多ければ、その分ポットの数を増やします。要はピッチャー代わりに、注ぐ専用のポットを用意するということ。なあんだ、とお思いかもしれませんが、ルピシアのティーサロンでも、大勢のお客様に同じお茶をいれるときはこの方法。濃い・薄い、熱い・ぬるいのムラが出ず、全員に同じおいしさでいれられます。
通常のポットでなくても、茶こし付き・耐熱ガラス製の
ルピシアハンディークーラーなら一度に7~9人分、ハーフでも4~5人分を簡単に準備できます。


千利休によって完成されたという茶の湯(茶道)は、現代では残念ながら堅苦しいイメージを持たれています。でもその本質は、日本のおもてなしの心そのもの。お茶や茶道具、掛け軸やお花などをすべて総合芸術として演出する、インテリアコーディネートとテーブルセッティングの元祖なのです。
茶の湯に学べる最もシンプルで効果的な技は、季節感を取り入れること。たった一輪の花を飾るだけでもテーブルはぐっと華やぎます。季節のお茶請けを選び、メッセージカードでも添えれば、リビングはもう現代のお茶席です。


お茶席のセッティングを決めたら、主役のお茶もきちんと決めたいもの。お茶は、どんなに高級な紅茶・日本茶・烏龍茶でも、1杯分の値段を計算すればお手頃なもの。例えば同じ嗜好品のワインなら、ちょっとしたもので1本数千円以上しますが、お茶ならばおこづかい程度で世界の最高級品を何杯も味わえます。
選び方の基本は、まずは会話が弾みやすい季節感を演出。今ならサクラのお茶などが最適。また、同じ種類や産地のお茶を農園別などのテーマを決めて飲みくらべてみるのも楽しいですね。
食事と一緒なら、例えば食前には風味や香りがいい烏龍茶を少量。食中茶にはジャスミン茶やほうじ茶などのクセのないものを。そして食後の口直しには、さっぱりした日本茶やセイロン・ウバ、ダージリン夏摘み紅茶など選んではいかがでしょうか? いつもと違う会話が盛り上がります。


もう一つ、茶の湯の伝統に学びたいのは、春ならではの「野点(のだて)」です。戸外を茶室に見立てた、比較的気軽な催し。だから、お気に入りのお茶を保温ボトルに詰めて野山にでかけるだけで、もう気分は野点です。
例えば春の行楽を兼ねてアウトドア用のバーナーと茶器をリュックに詰め、山水を沸かし、本格的にお茶をいれてみましょう。景色の良い場所でいただくお茶は、普段よりもぐっと風味がよく感じられます。
そんな本格的なことは難しいという方は、例えばお天気の日に窓を開けて陽射しを浴びながら、また庭や公園などでお茶をいただくだけでも、春の野点気分が満喫できます。