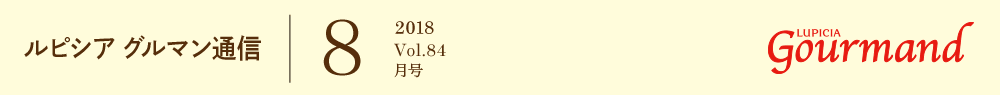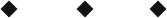夏の体にうれしい野菜
トマトは南米アンデス山脈地方原産のナス科の植物。日本には江戸時代(1660〜70年代)、長崎に伝わりました。当時は独特の酸味、赤い色が敬遠され「唐柿(とうがき)」などと呼ばれ観賞用として栽培されていました。
日本人がトマトを食べるようになったのは明治以降。昭和に一般的な野菜として普及しました。
ヨーロッパではリンゴと同様に「トマトが赤くなると医者が青くなる」という諺(ことわざ)がある健康野菜。特にトマトに含まれる色素の一つリコピンは、ビタミンEの約100倍とも言われる抗酸化作用があることで知られています。
またトマトは体内でビタミンAに変化するβ-カロテンをはじめ、ビタミンC、ビタミンB1、ビタミンB2、ビタミンE、カリウム、カルシウム、マグネシウム、鉄、亜鉛などのミネラルを含んでいます。
さらにトマトの酸味はさっぱりとした口当たりで、食欲をそそります。夏の体の疲れをいたわるクエン酸の含有量は野菜類の中でもトップクラス。トマトは暑い夏にぴったりの食材なのです。
北海道は名産地
世界では8,000種以上、日本でも120種超の品種が登録されているトマト。
国内生産量のトップは熊本県ですが、北海道はそれに次ぐ一大トマト生産地。梅雨の無い北海道は高品質なトマトの栽培に最適な土地です。年間生産量56,900トン、国産トマトの約8.5%(2017年)を生産しています。 道産トマトの最盛期は8月。ヴィラ ルピシアのある北海道・ニセコ周辺の農家の直販所は、夏になると赤や黄、大小さまざまなトマトで満たされます。
近年、避暑地として注目を集めるニセコ。日本はもちろん、世界各地から集まる滞在者のお目当ての一つが、トマトを代表とするニセコのおいしい夏野菜であることにも大いに納得です。