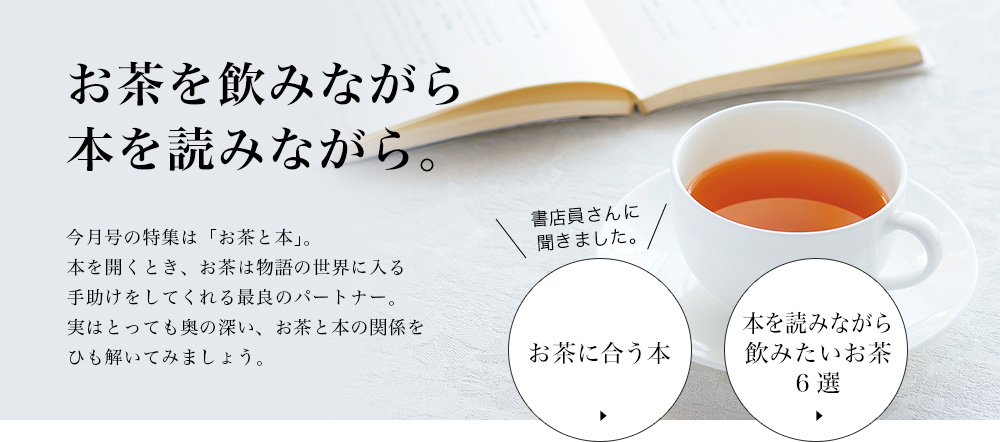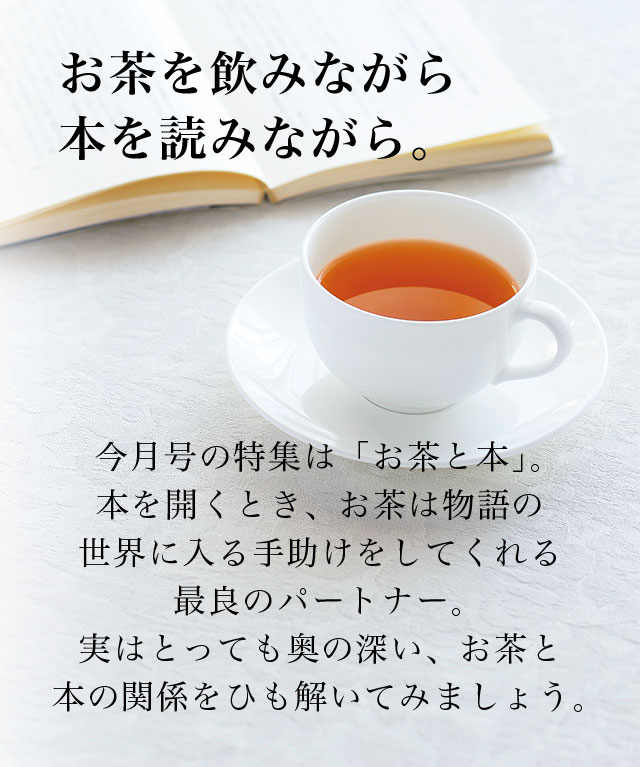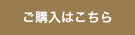心地よい読書のために
さあ、これから本を読もうという時、何をしますか?
家の中で長時間座っていても疲れない、読書に最適の場所を探し、お気に入りのクッションを背に置き、手の届く範囲にお菓子とブランケットを用意します。
そうして環境を整えたら、お茶をいれる準備をします。これから読む本に合うお茶は何かと思いをめぐらせ、茶葉を選び、シュンシュンと音を立てるケトルからティーポットにお湯を注ぐ……。
読書へ向かうこの一連の小さな儀式にも似た作業は、それ自体が読書をするための導入、読書の一部のような気さえします。
お茶と本、関係がないように見えて、どちらもプライベートな時間に安らぎと彩りを与えてくれるという共通点があります。