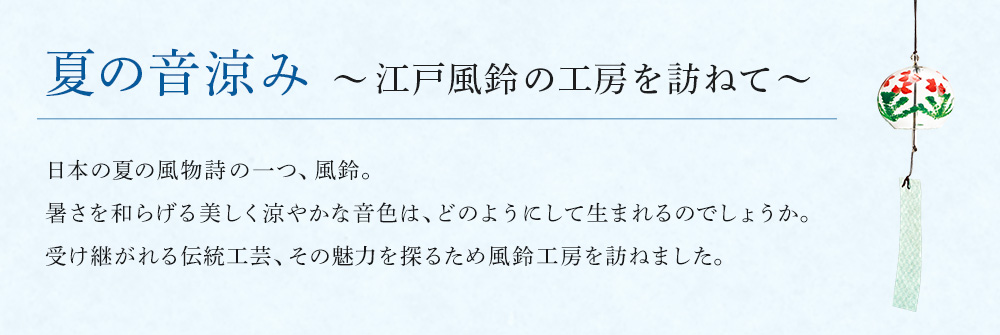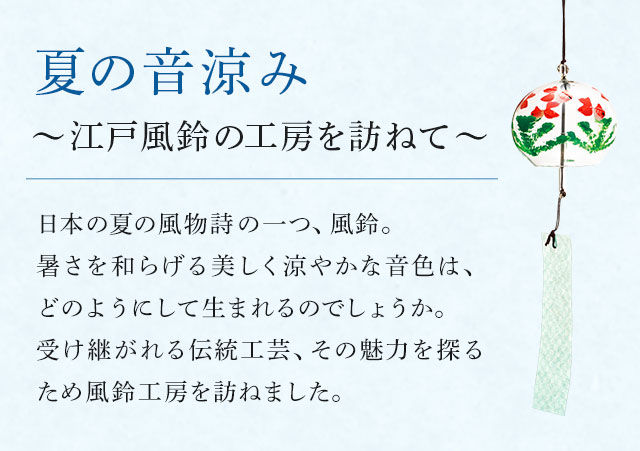300年の伝統「江戸風鈴」
東京・江戸川区に位置する「篠原風鈴本舗」。300年の歴史を持つ伝統工芸「江戸風鈴」を作り続けてきた、老舗の風鈴工房です。江戸風鈴とは、それまでガラス風鈴と総称されていたものを、“江戸時代からの伝統を受け継ぐ工芸品”として、1964(昭和39)年頃に風鈴職人の篠原儀治(しのはら よしはる)さんが名付けたもの。現在、江戸風鈴の製作を行うのは篠原風鈴本舗を含め2カ所のみになりました。
 篠原風鈴本舗の工房。屋号の暖簾がかかる風情ある佇まい。
篠原風鈴本舗の工房。屋号の暖簾がかかる風情ある佇まい。 原料となるガラス。美しい透明感が涼を誘います。
原料となるガラス。美しい透明感が涼を誘います。
唯一無二の音色
江戸風鈴の特徴は、職人の手仕事により生み出される唯一無二の音。高温で溶かしたガラスを成形していく際、型を使わずに「宙吹き(ちゅうぶき)」と呼ばれる手法をとるため、出来上がる風鈴は一つとして同じものはありません。大きさ・形・厚みの僅かな差が、音の高低や響きに大きく影響します。
「風鈴の音色というのは、均一に響かないからこそ人を魅了する力があります」。そう語るのは、江戸から代々続く風鈴工房「篠原風鈴本舗」の篠原恵美さん。「一人前になるまでに20年はかかると言われる風鈴職人でさえも、出来上がりを鳴らしてみて初めて、どんな音に仕上がったのかが分かる」のだそう。
 高温のガラスを友竿(ともざお)に巻き取り、成形していきます。
高温のガラスを友竿(ともざお)に巻き取り、成形していきます。 宙吹きの様子。一切の無駄のない所作が体に染みついているそう。
宙吹きの様子。一切の無駄のない所作が体に染みついているそう。
風鈴は風鈴本体とその下に吊られた舌(ぜつ)というガラス棒が風に揺れて当たることで音が鳴りますが、江戸風鈴の作りは他とはひと味違います。本体のふちを切り落とす際、あえてギザギザの不均一な状態のままにし、本体と舌が当たる音だけでなく、擦れ合う音も重なって聞こえるようになっています。その不均一なゆらぎが生み出す音色こそ、私たちを魅了してやまない江戸風鈴の魅力。
驚くべきことにその音色は、リラックス効果を持つと言われる鈴虫の声と同じ周波数だそう。「もともと魔除けや風水としての起源を持つ風鈴が、今や夏の風物詩として馴染み深くなったのは、その音色の心地よさが関係しているのでは」と恵美さんは話します。
 ガラスを巻き取り膨らます作業を2回繰り返すため、ひょうたん型になります。
ガラスを巻き取り膨らます作業を2回繰り返すため、ひょうたん型になります。 鳴り口のギザギザ部分をあえて滑らかにしない手法は、江戸風鈴ならでは。
鳴り口のギザギザ部分をあえて滑らかにしない手法は、江戸風鈴ならでは。
職人の技光る絵付け
「音もさることながら、描かれた絵やその色遣いというのも風鈴の魅力の一つ。音色の仕上がりと同等に、我々が力を注いでいる部分でもあります」。恵美さんが主に担当されるのは絵付け。
風鈴が夏の風物詩として広く親しまれるようになったため、最近ではすっかり輸入品が多くなってきましたが、江戸風鈴が他の風鈴とは異なるのは音だけではありません。その大きな特徴は、ガラスの内側から絵付けを行うこと。大小の筆を使い分けながら、一色塗っては乾かし、また次の色を重ね・・・と繰り返して少しずつ絵が浮かび上がってきます。
内側から絵付けをすることで、ガラス表面の艶やかな光沢が失われることがなく、雨や風によって色が剥がれることを防げるそうです。「作り手からすれば、乾かす間にうっかり表面に触れてしまっても手に付かない、というメリットもありますね(笑)」と恵美さん。
実際に絵付け作業を見学し気づくのは、完成形の絵の裏表を反転させて描いていく難しさ。下書きが出来ないため、長年の経験で培われた技術あってこその美しい仕上がりになります。絵付けの工程だけで、長いものだと3週間にも及ぶのだそう。
「最近では、夏を感じさせる金魚や花火の絵柄が好まれますが、伝統的な紋様も根強く人気がありますし、その時々の話題を反映させたユニークなものも作ってみたり、皆さんに風鈴を楽しんでもらいたい一心で色々工夫しています。お気に入りの音、お気に入りの絵柄をぜひ見つけてほしい」と恵美さんは話します。
音色も絵柄も一つ一つ手作りするからこそ、同じものは他に一つとない江戸風鈴。この夏はお気に入りの風鈴で、心地よく涼んでみませんか?
 全体のバランスをとるのも球体に絵付けする難しさ。
全体のバランスをとるのも球体に絵付けする難しさ。 恵美さん愛用の、年季の入った道具。
恵美さん愛用の、年季の入った道具。