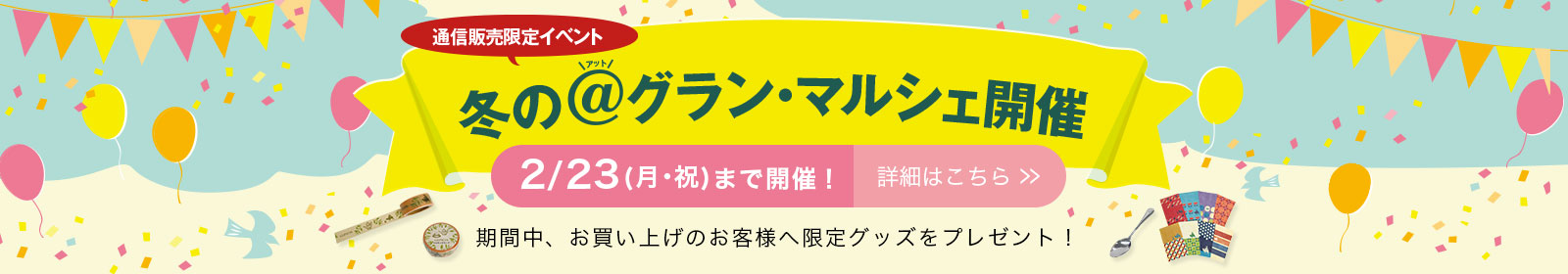「手揉み製茶」とは?

文化庁による無形文化財登録の検討が進められている(2025年現在)など、近年、お茶愛好家の注目を集めている「手揉み製茶」による玉露や煎茶。工芸品や芸術品のように手間をかけて作られる“ 食の文化遺産” と呼ぶべき逸品です。
この「手揉み製茶」の原型は、元文3 年(1738)、京都・宇治の永谷宗円が確立した「青製(あおせい)煎茶」にあります。蒸した茶葉を焙炉(ほいろ)と呼ばれる作業台で、炭火などの熱を利用して揉みながら乾かす製茶法です。従来の中国式の釜炒り製茶や、蒸した茶葉をむしろの上で乾燥させるなどして作られていた当時の煎茶や番茶と比べ、その品質は画期的でした。
その後、日本茶は幕末から明治期の開国と海外貿易の活発化により、生糸と並ぶ重要な輸出品となります。様々な製法や技術が乱立する中、品質向上や粗悪品対策のために工程の統一が進められ、大正4 年(1915)、お茶輸出の中心地であった静岡にて「手揉み製法」は標準的な製法として確立されました。この製法をもとにした技術が、現在も宇治、狭山、八女など各地で受け継がれています。
「手揉み製茶」は、一人前の職人と認められるまで10 年以上の修行が必要とされる匠の製法。機械化による効率ではなく、お茶づくりの原点といえる技と品質を追求し、手のひらの繊細な力と体温に近い低温で、5 〜6 時間以上をかけて揉み込まれた茶葉の味わいは、日本茶ならではの繊細さと力強さを併せ持つ、まさに特別なおいしさです。

大正時代に出版された宇治の焙炉による製茶作業場写真。京都茶業写真総覧(1924)より。

熱源となる焙炉(ほいろ)の上に、助炭(じょたん)と呼ばれる和紙を貼った木枠を載せて、茶葉を加熱・乾燥しながら手作業で製茶する(静岡・岡部)。

幕末から明治・大正にかけて手揉み製法で作られた日本茶は、ミルクや砂糖にも負けない力強い味わいの緑茶として、米国を中心として高く評価された。
ITEM

朝比奈玉露 手揉み製法
宇治、八女と並ぶ玉露の名産地・静岡県朝比奈。 「岡部町茶手揉保存会」による、伝統的な手作業で6時間以上かけて仕上げられた手揉み玉露。
詳しく見る